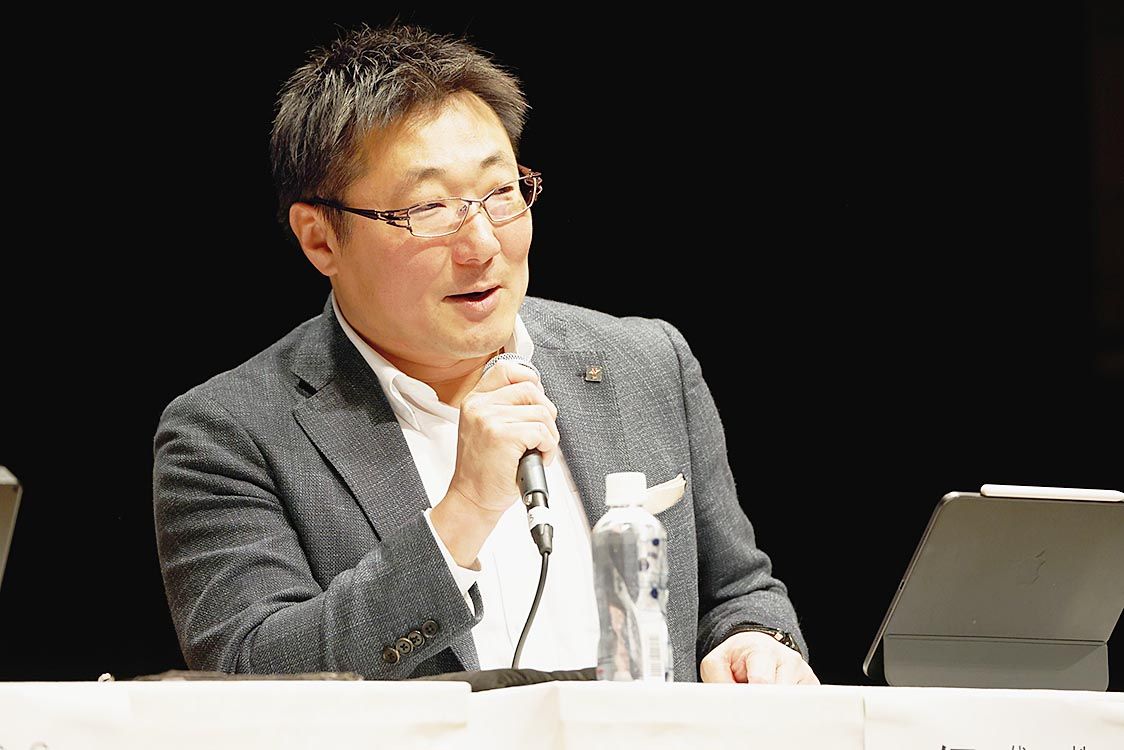日刊自動車新聞社・花井真紀子社長「自動車産業は大変革期の最中、将来に向けて多くの力を結集する必要がある。国内マーケットは人口減少の中で厳しさが増すことが予想される。それでも次の世代のために日本の活力を高めていきたいし、自動車産業にはそのポテンシャルがあると思っている。新しい価値を創造し、広がりをつくり、新しい産業を興していく。地域に根差し、発展してきた自動車産業だからこそ、その中核になれると考える。今回は、それを実践している自動車販売会社の皆さんに登壇してもらっている。社会的な問題を解決しながらいかに新しい価値を創造し、持続的な発展につなげているか。まずはそれぞれの会社が掲げているスローガンとともに紹介してもらい、進もうとしている方向性について教えてもらいたい」
TSA(トヨタカローラ秋田/秋田トヨペット)・伊藤哲充社長「すべての人に移動の自由を─。モビリティ社会になると言われて久しいが、一般の人はピンとこない。モビリティの本質として、その人の状態にかかわらず行きたいところに行けたりモノが届いたり。それを一言で表した」
GNホールディングス・渡邉将マーケティング戦略部部長「Going Limitless─。『リミッターを外して突き進んでいこう』ということ。当グループは1925年の創業。関東大震災の2年後で、当時は日産車ではなく『T型フォード』などを売っていた。当時、自動車産業に乗り出そうというのはおそらく、相当に変わった人たちがそれなりに大きな志(こころざし)を持って臨んだのだろうと想像できる。それから100年が経ち、成功体験に甘えたり、常識にとらわれたり『壁の内側』に住むことがおそらく続いている。先の100年を生きていくためには、それではいけない。比較的にこの言葉があるおかげで挑戦しやすくなった」
神戸マツダ・橋本覚社長「5 HAPPY─。パーパス、企業理念と言っても過言でない。1つは『お客様の幸せ』。マツダは新世代店舗を進めているが、2030年までにすべてを新世代店舗に変えた上で、一つひとつの店舗に個性を持たせる。次は『社会・環境の幸せ』。女性の社会進出に少しでも役立とうと保育園をオープンした。4月には整備学校を開校する。整備士不足の中で少しでも選択肢を増やしたい。また、環境については30年までに二酸化炭素(CO2)排出を半減する。『協力者(パートナー)の幸せ』では『神戸マツダファンフェスタ』を年1回実施し、ここでパートナーを紹介している。『社員とその家族の幸せ』については、『ホワイト500』を8年連続で認定いただいている。社員が100%のパフォーマンスを出すためには健康でなければならない。『地域の幸せ』では兵庫区の南北交通を補完するための『みんなのバス』を走らせている」
トヨタカローラ香川・向井良太郎社長「モビリティで香川の未来を変えていこう─。移動の変革で地方を支える可能性があると感じている。当社は『生涯顧客』をつくりたいと考えている。自動車ディーラーのもともとの顧客は基本的に免許保有者だが、これからは違う。免許返納者も含め地域に合った移動サービスを提供していく。一方で、地方のMaaS(サービスとしてのモビリティ)はマネタイズが難しい。後ほど、マネタイズの仕組みはご紹介したい。もう一つは、トヨタ自動車は『もっといいクルマづくり』を掲げている。販売店は『もっと良いお店をつくろう』と。地元のディーラーが持っているもっと良いお店の要素は3つ。1つ目は小売業でありながら商社である。ディーラーほど顧客情報をしっかり持っている商売はない。2つ目はトヨタブランド。いろいろやろうと思った時にトヨタの看板があるからできることはありがたいし、これを最大限に生かす。3つ目は地元企業だということ。トヨタという世界的なブランドを掲げながら地元企業として提案ができる。これが強みであり、こういったアセットをうまく使っていく」
ホンダカーズ中央佐賀・大橋諄簡社長「50・RESTART!─。5月で株式会社にしてから50年になる。当社は佐賀県の西にある武雄が創業の地。そこにある2拠点を一つにして4月にオープンする。私たちは確かにメーカーブランドがある。でもホンダカーズ中央佐賀のブランドはあまりない。これからのディーラーは、地域にどれだけ根付けるかだと思っている。これから紹介する『asobiba』ではそこを意識して新しい形を見せていきたい」
花井社長「『場をつくる』取り組みについて、まずはホンダカーズ中央佐賀の事例を紹介してほしい」
大橋社長「創業の地である武雄はご多分に漏れず人口が減少しており、その中でどう地域と関わってくるかというのが課題だ。広い土地が確保できそうだとなった時に『武雄は公園が少ないな』とふと考えた。店舗はもちろん人が集まる場だが、もっと違う観点で人が集まる場をつくりたいというのが入り口だ。私は別の業界からクルマ業界に入ったので、ディーラーは敷居が高いと今でも思っている。だから『どれだけ敷居を下げられるか』に挑戦していこうと。公園をつくる時に面積が1万平米を超えると貯水池をつくらないといけない。武雄では19年、21年と豪雨災害があり、当社の2拠点でも被害にあって何十台も水に浸かった。貯水池をつくらなければならないなら、それをうまく利用して公園をつくれないかと」
花井社長「次は『移動をつくる』をテーマに話をしていただきたい。秋田県横手市では有償乗り合いサービスを実施し、人の流れをつくることで活性化につなげている」
伊藤社長「横手市の狙半内(さるはんない)という地区だが、秋田でも知らない人には地名が読めない。どうもルーツがアイヌにあるということで話している言葉も違う。『どすめかす』というこの地域の方言があって『急いで』という意味だが、送迎を電話で頼むときに市の職員とコミュニケーションが取れない問題があった。これがサービスをやっていて気付いたことで、多くのサービスをやっていく上で原点となったのが狙半内だ。利用者は高齢者が多いが、便利になれば工夫するようになって、病院や買い物だけでなく娯楽にも使うようになる。便利になれば年齢を問わず使いたくなる。『人が移動すると街が元気になる』というのが最大の学びだ」