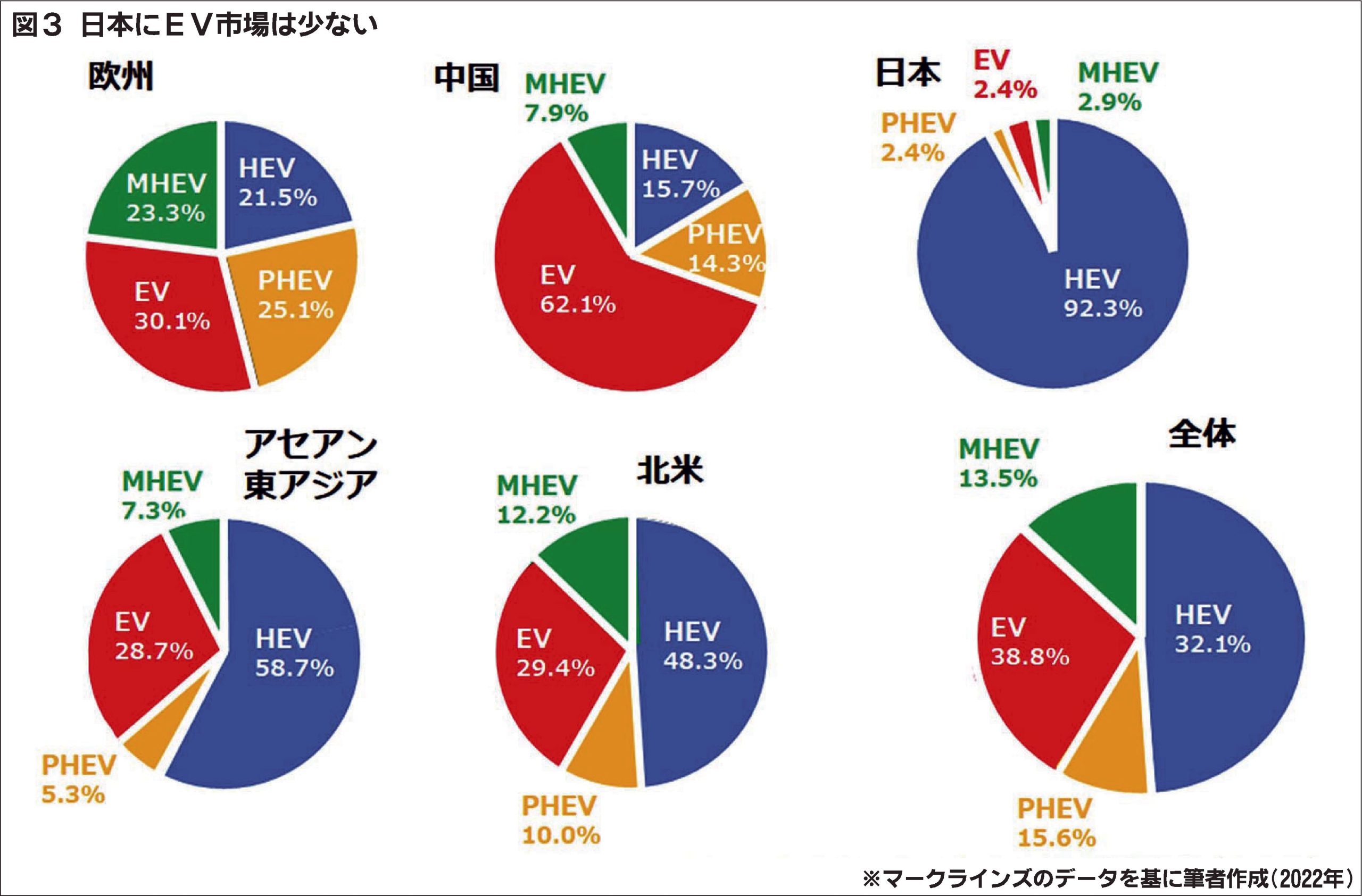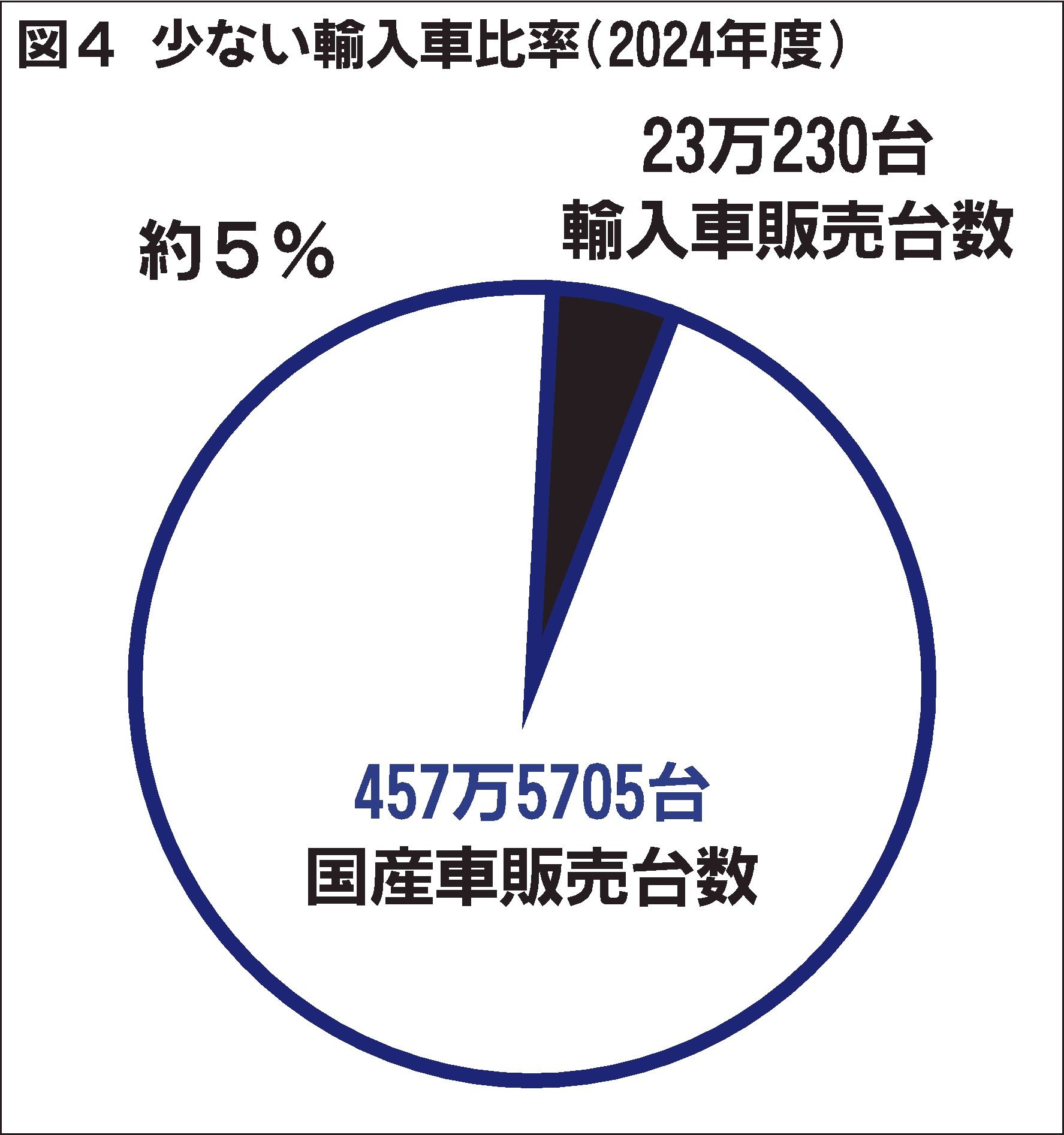関連記事
連載「ガンバレ ! 自動車産業」(29)PHEVはエコカーの切り札か? 繁浩太郎
- 2025年6月25日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「ガンバレ!自動車産業」(28)日本の自動車産業の終焉? 繁浩太郎
- 2025年5月28日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「ガンバレ!自動車産業」(25)カーメーカーの商品開発体質 繁浩太郎
- 2025年2月26日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「ガンバレ!自動車産業」(24)ホンダと日産と日本のこと 繁浩太郎
- 2025年1月29日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

三菱ふそう、「キャンター」を一部改良 燃費と利便性を向上
- 2026年2月17日 05:00|自動車メーカー