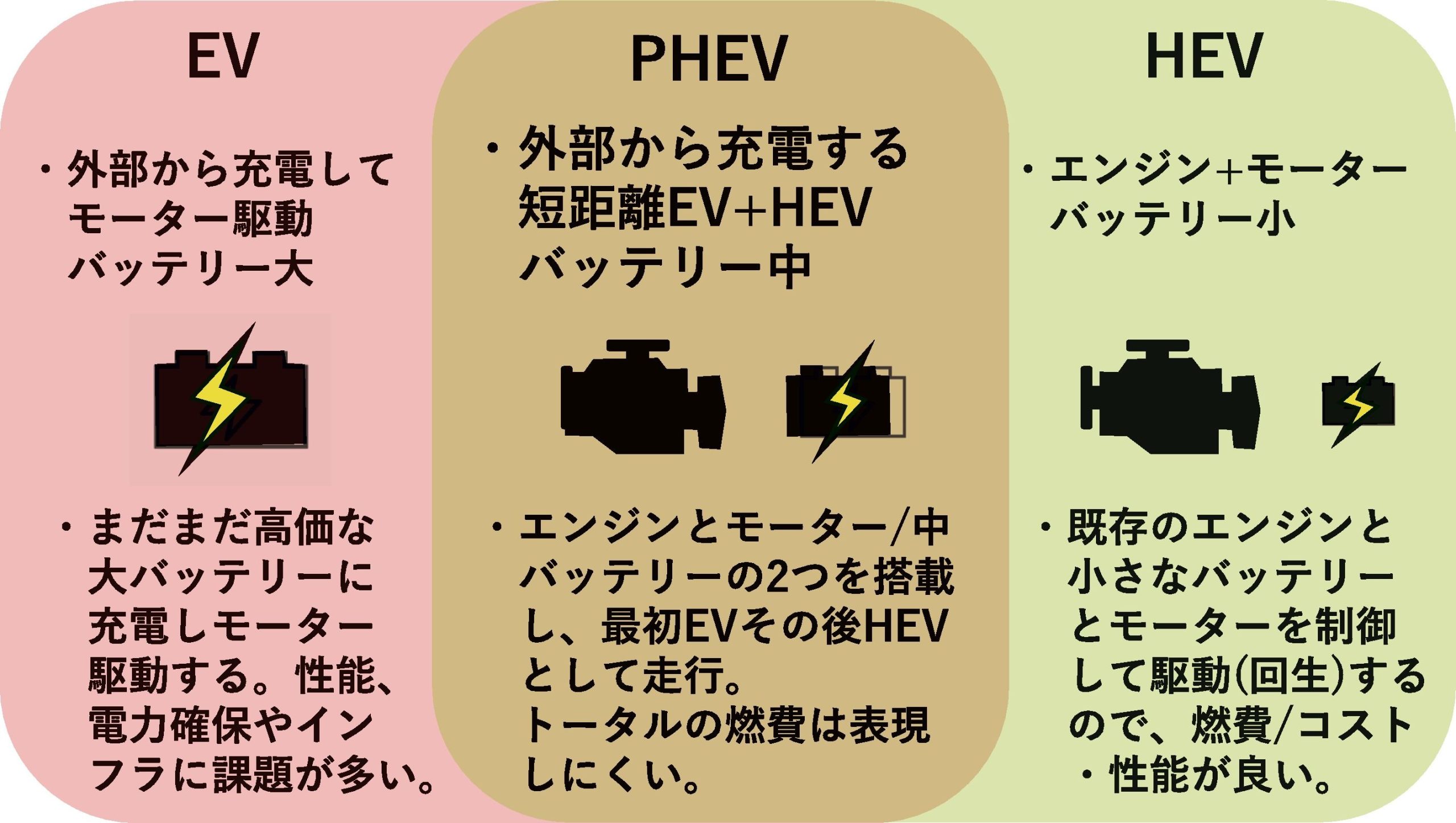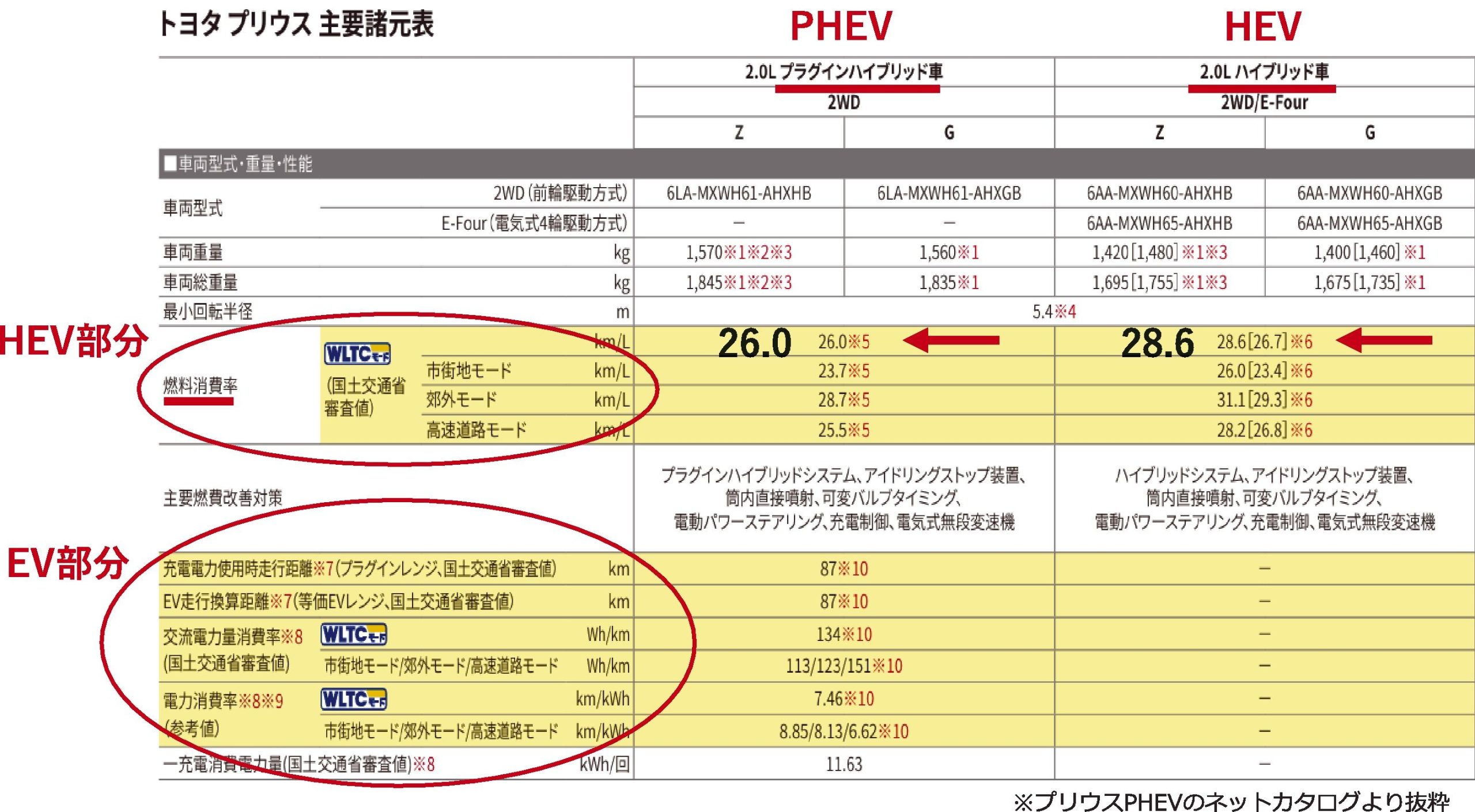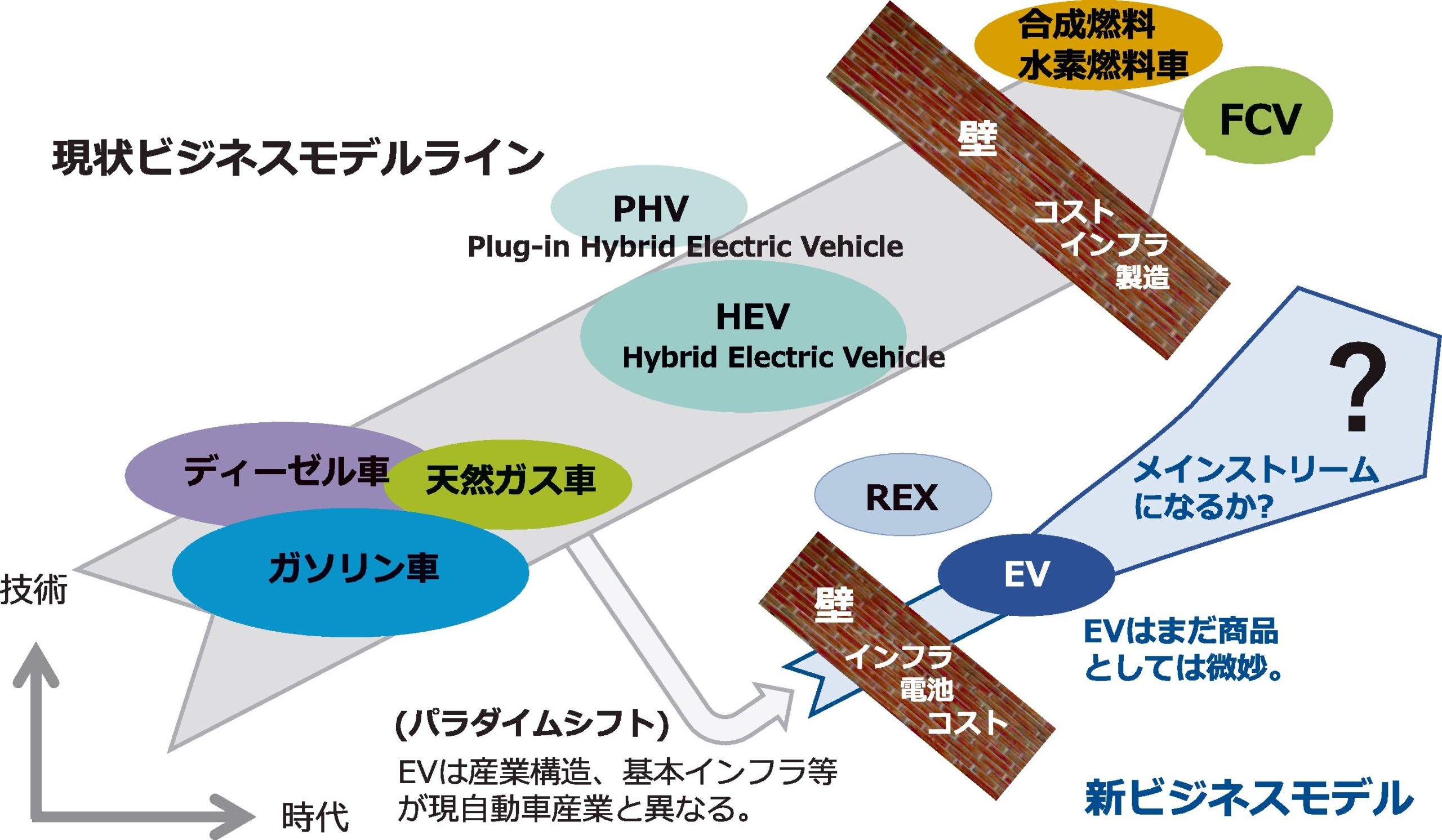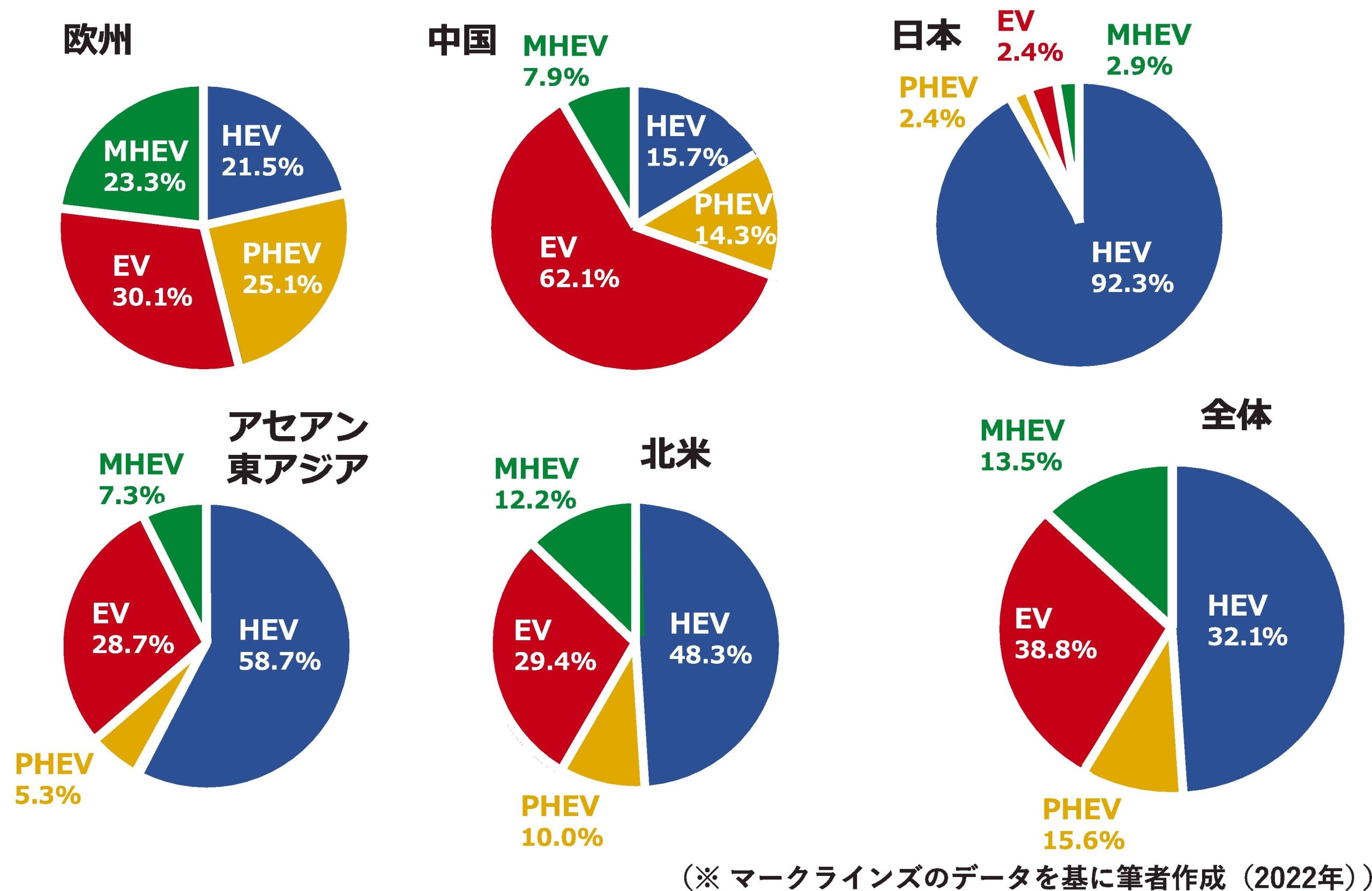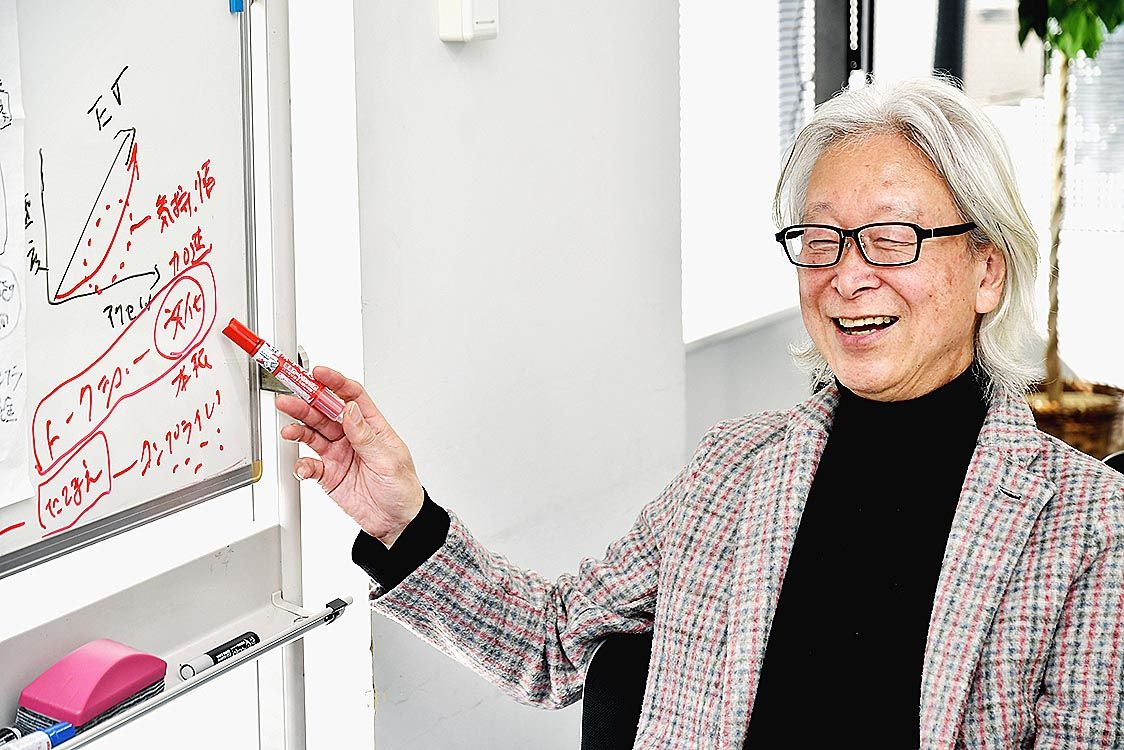関連記事
連載「ガンバレ!自動車産業」(28)日本の自動車産業の終焉? 繁浩太郎
- 2025年5月28日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「ガンバレ!自動車産業」(25)カーメーカーの商品開発体質 繁浩太郎
- 2025年2月26日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「ガンバレ!自動車産業」(24)ホンダと日産と日本のこと 繁浩太郎
- 2025年1月29日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 連載・インタビュー

連載「私のホンダ記録」(33)ブランド編 繁浩太郎
- 2023年1月26日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

連載「私のホンダ記録」(28)N-BOXシリーズの開発(1)繁浩太郞
- 2022年9月24日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー