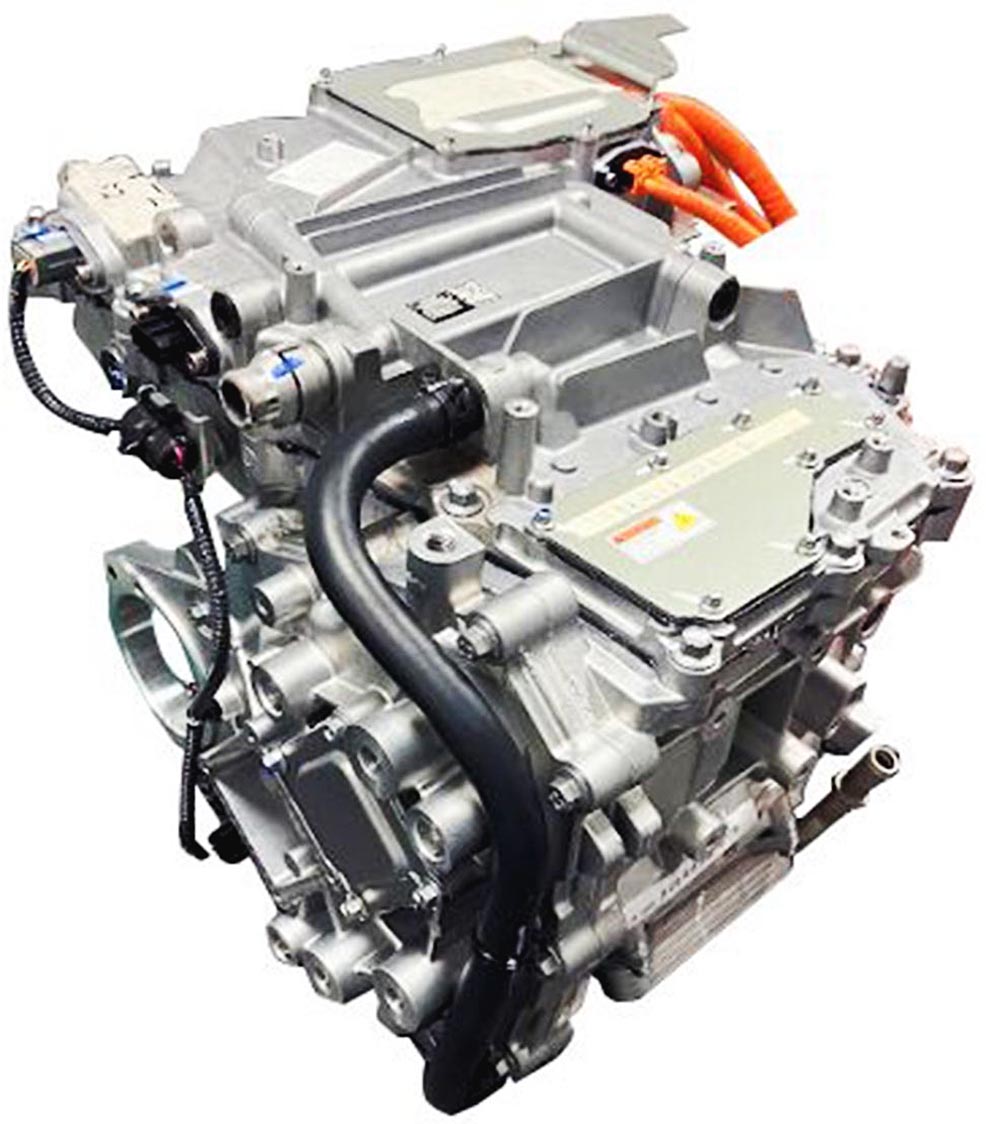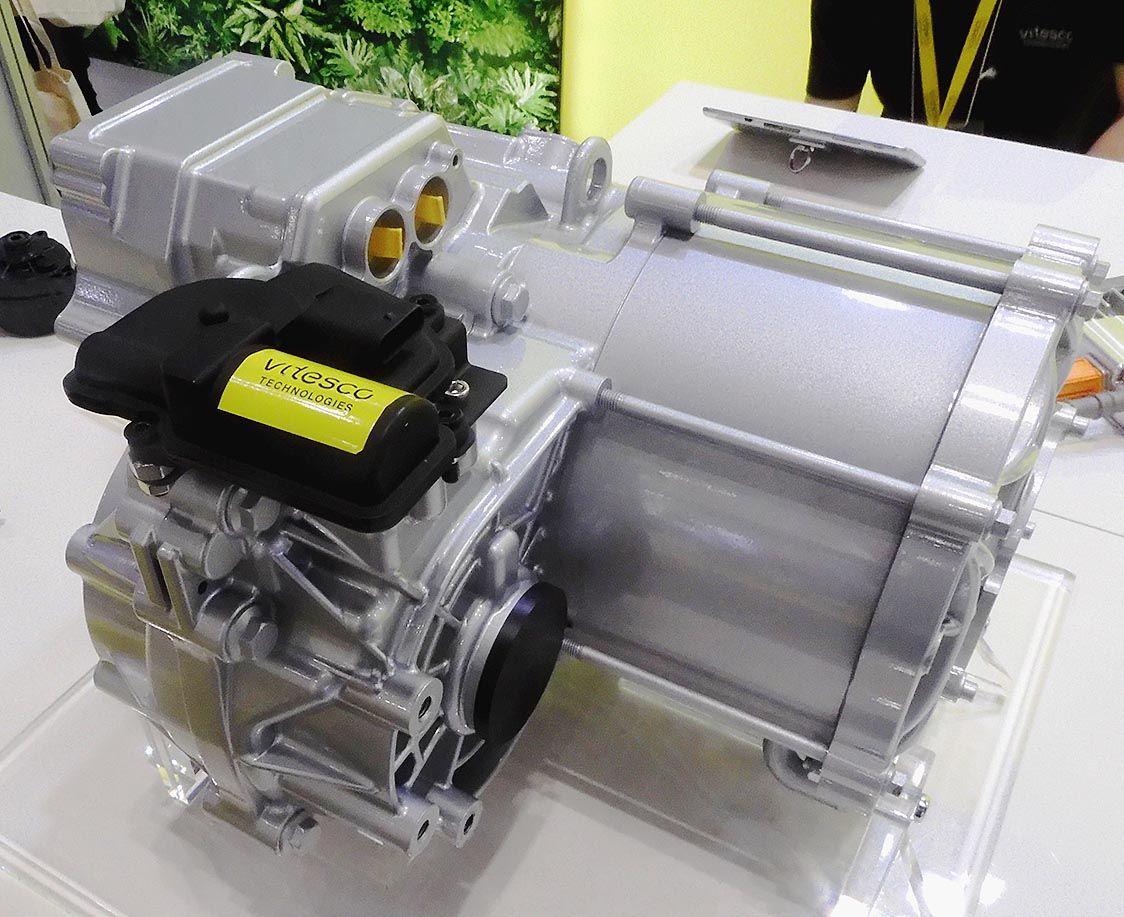関連記事
厳しい生存競争「eアクスル」 自動車メーカーは内製化の動き 合従連衡も必至
- 2024年9月11日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 自動車メーカー

ニデック、車載モーターの成長戦略見直し HV向けに注力しeアクスルは投資凍結
- 2024年7月25日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

ニデック、eアクスルの事業計画を見直し 投入モデルを一部白紙へ
- 2024年4月25日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

ニデックがトップ交代、ソニー出身の岸田光哉氏 “永守依存”からの脱却なるか 課題は車載事業の早期再建
- 2024年2月14日 19:50|自動車部品・素材・サプライヤー

ニデック、新社長に岸田光哉副社長が昇格 永守重信会長はグローバルグループ代表に
- 2024年2月14日 15:40|自動車部品・素材・サプライヤー

スバル「ゲレンデタクシー」体験記 雪上で真価を見せる走行性能 新たな“世界観”どこまで広げられるか
- 2026年2月14日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車メーカー