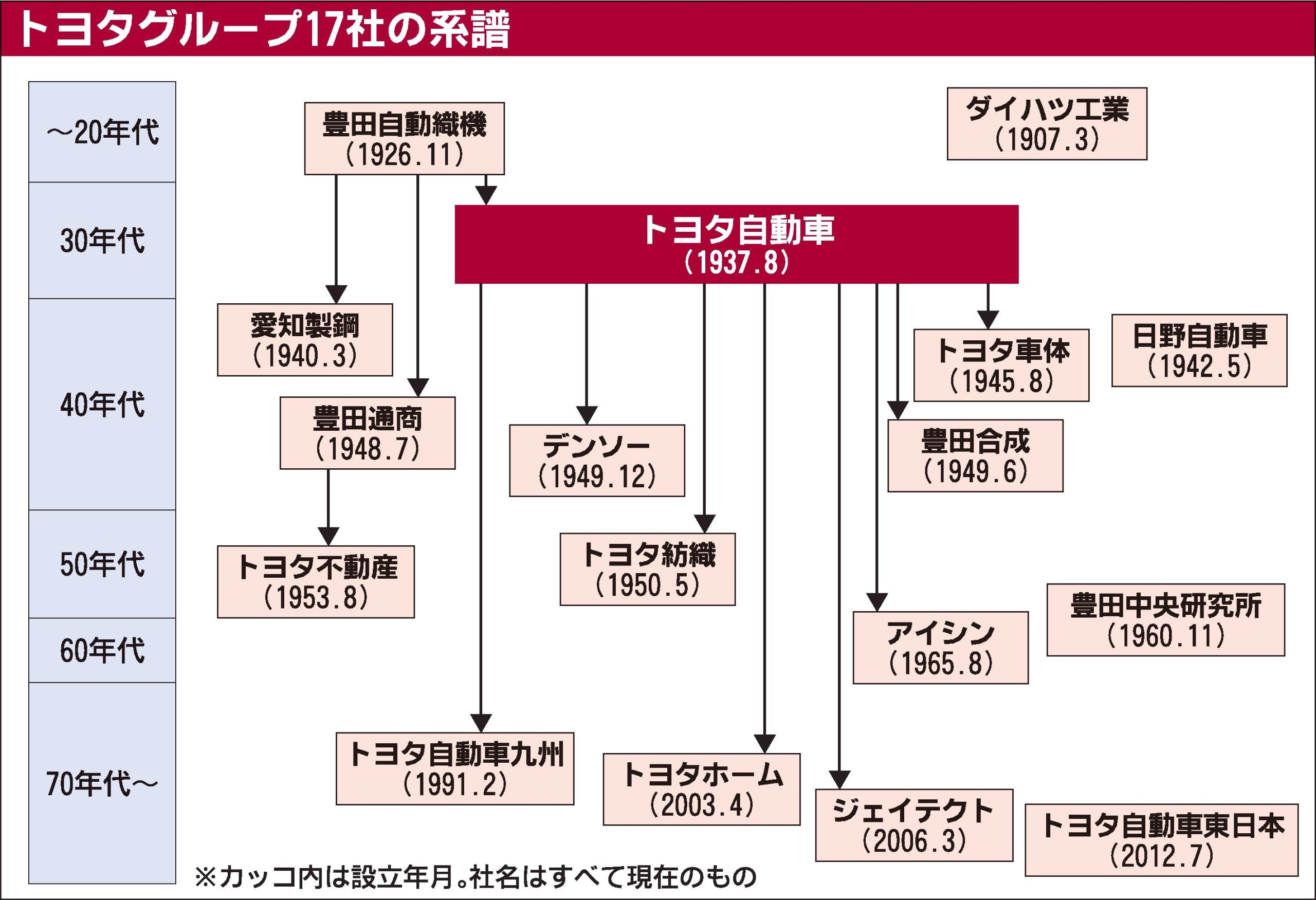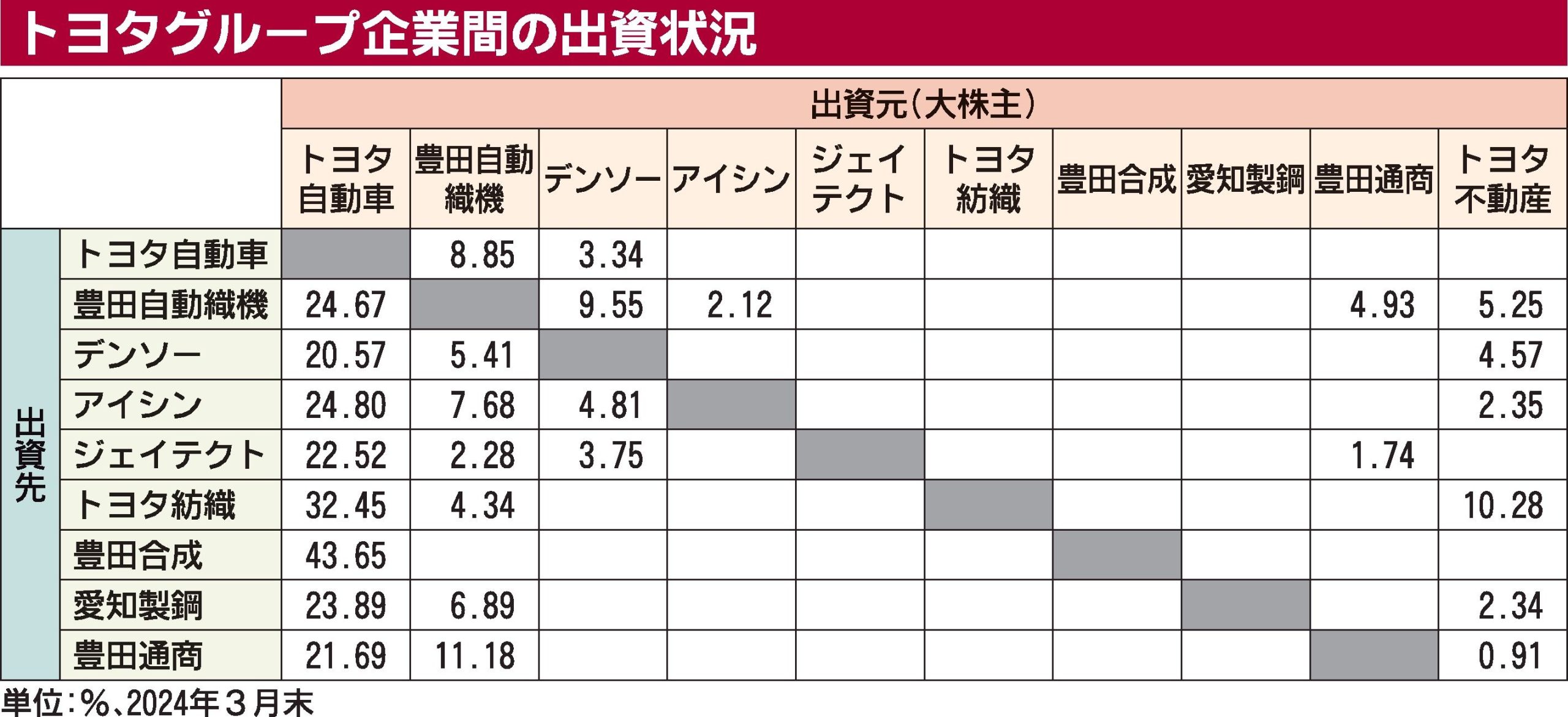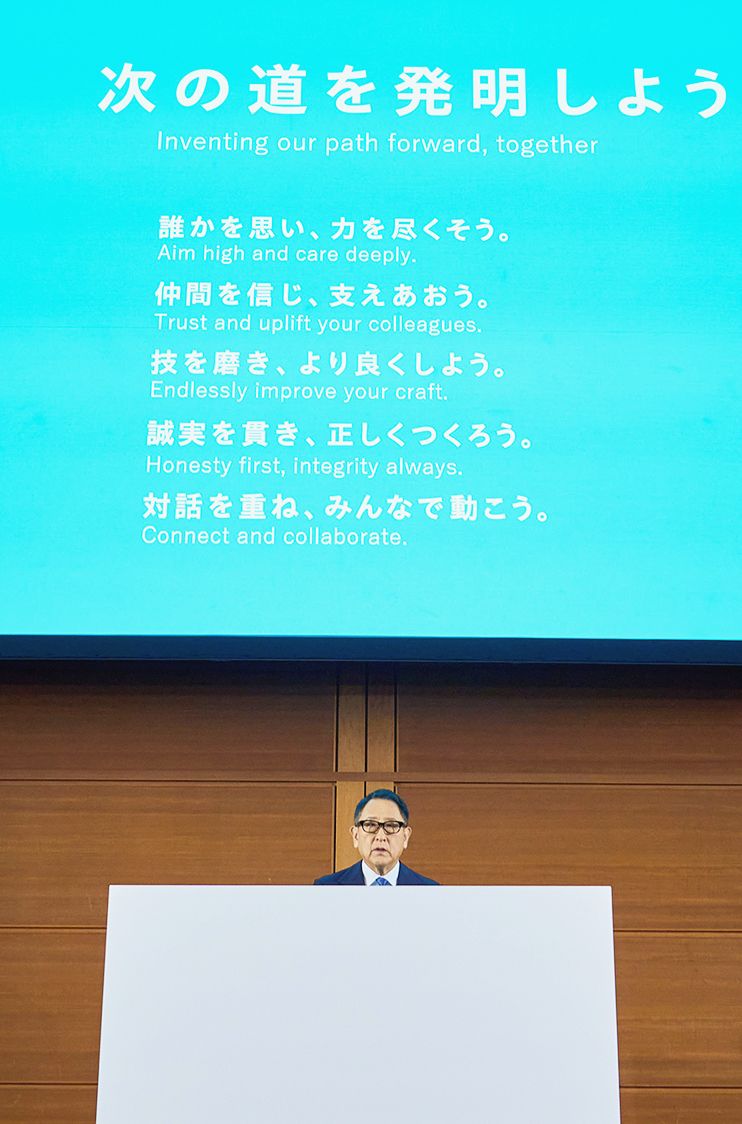関連記事
トヨタ、メガバンクや損保から自社株をTOB 発行済み株式の2%を8068億円で取得
- 2024年7月23日 20:10|自動車メーカー

トヨタ・ヤマハ・三井住友海上がヤマハ発動機の株を売却 政策保有株の解消で
- 2024年8月26日 05:00|自動車メーカー

損保大手4社の政策保有株、トヨタとホンダ株の売却で8000億円 非上場株も課題に
- 2024年8月26日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車流通・新車ディーラー, 自動車メーカー

トヨタ株主総会、豊田章男会長の再任 賛成は72% 昨年から12ポイント低下 米国助言会社が反対推奨
- 2024年6月19日 17:40|自動車メーカー

〈ニュースの底流〉グループで相次ぐ不正、正面から向き合うトヨタ 深刻な危機感 長期的な視野で再発防止策
- 2023年5月16日 05:00|自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン