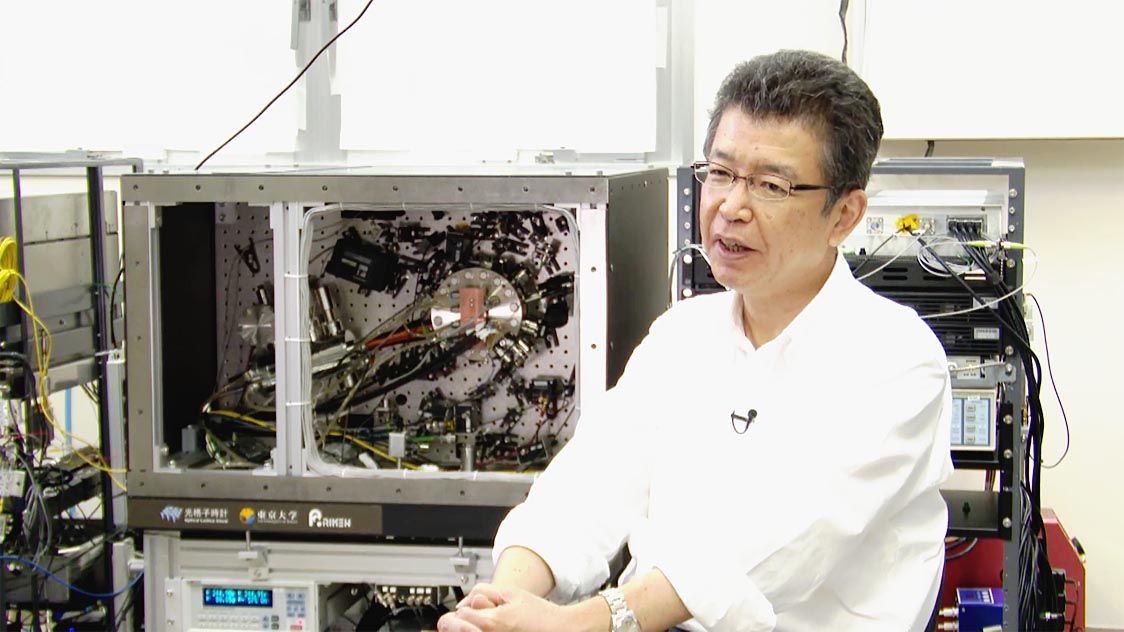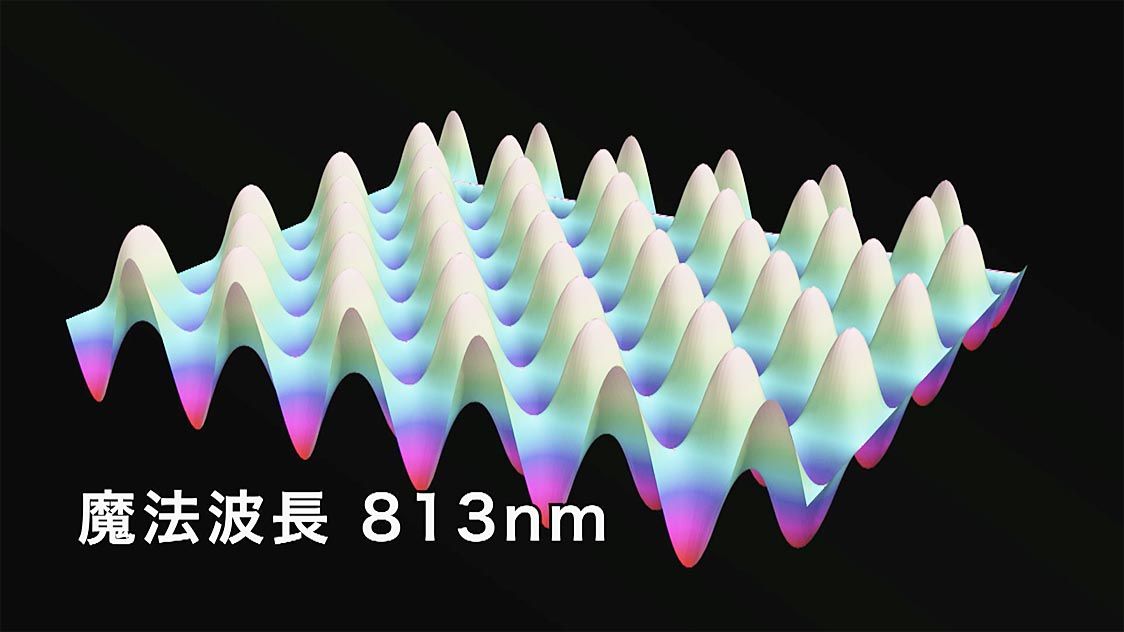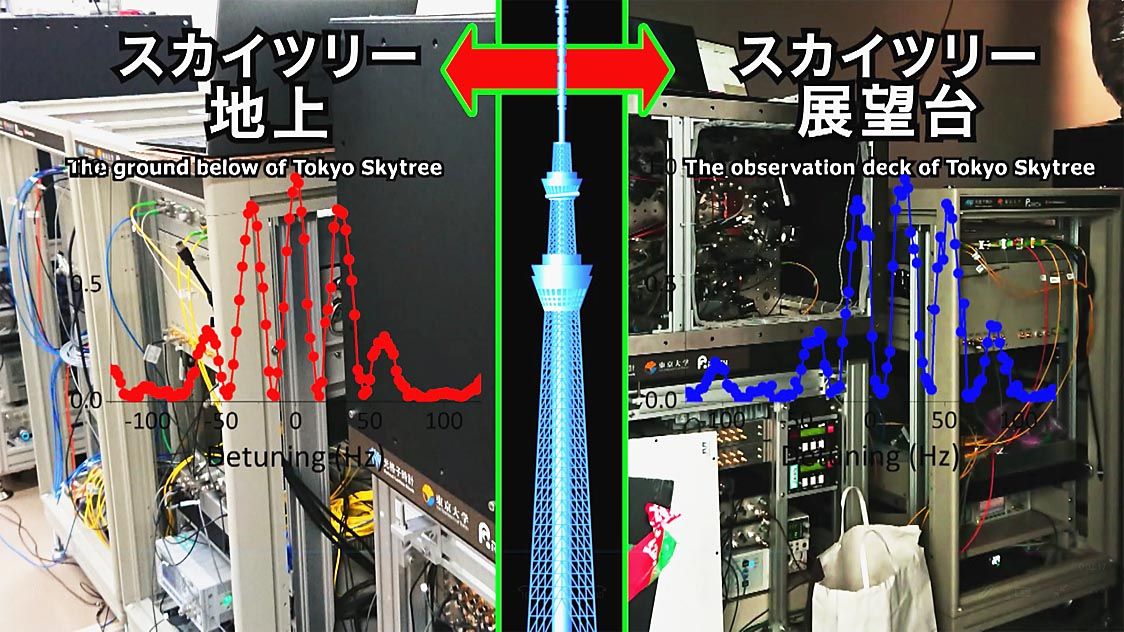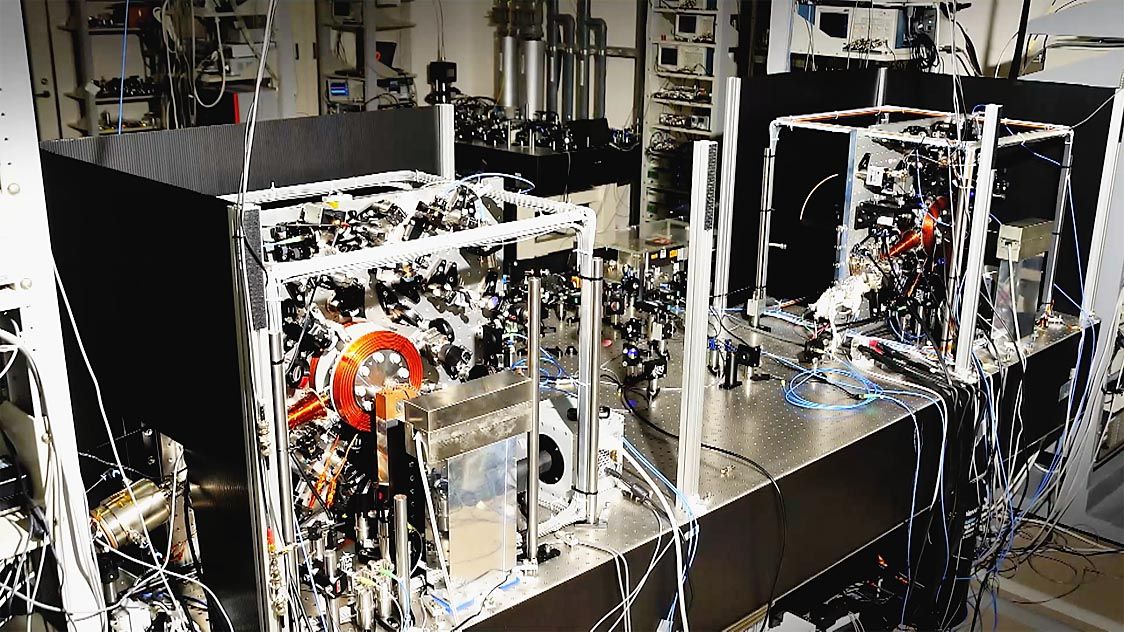関連記事
ホンダ、中国3工場の稼働停止を1月16日まで延長 半導体供給不足の影響続く
- 2026年1月5日 15:00|自動車メーカー

〈年頭所感2026〉川崎重工業社長 橋本康彦
- 2026年1月5日 11:30|自動車メーカー

〈年頭所感2026〉スズキ社長 鈴木俊宏
- 2026年1月5日 05:00|自動車メーカー

〈年頭所感2026〉三菱ふそうトラック・バス社長 カール・デッペン
- 2026年1月5日 05:00|自動車メーカー

日本自動車工業会、佐藤恒治新体制が発足 米中リスクなど課題対応をトヨタがリード
- 2026年1月5日 05:00|自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン