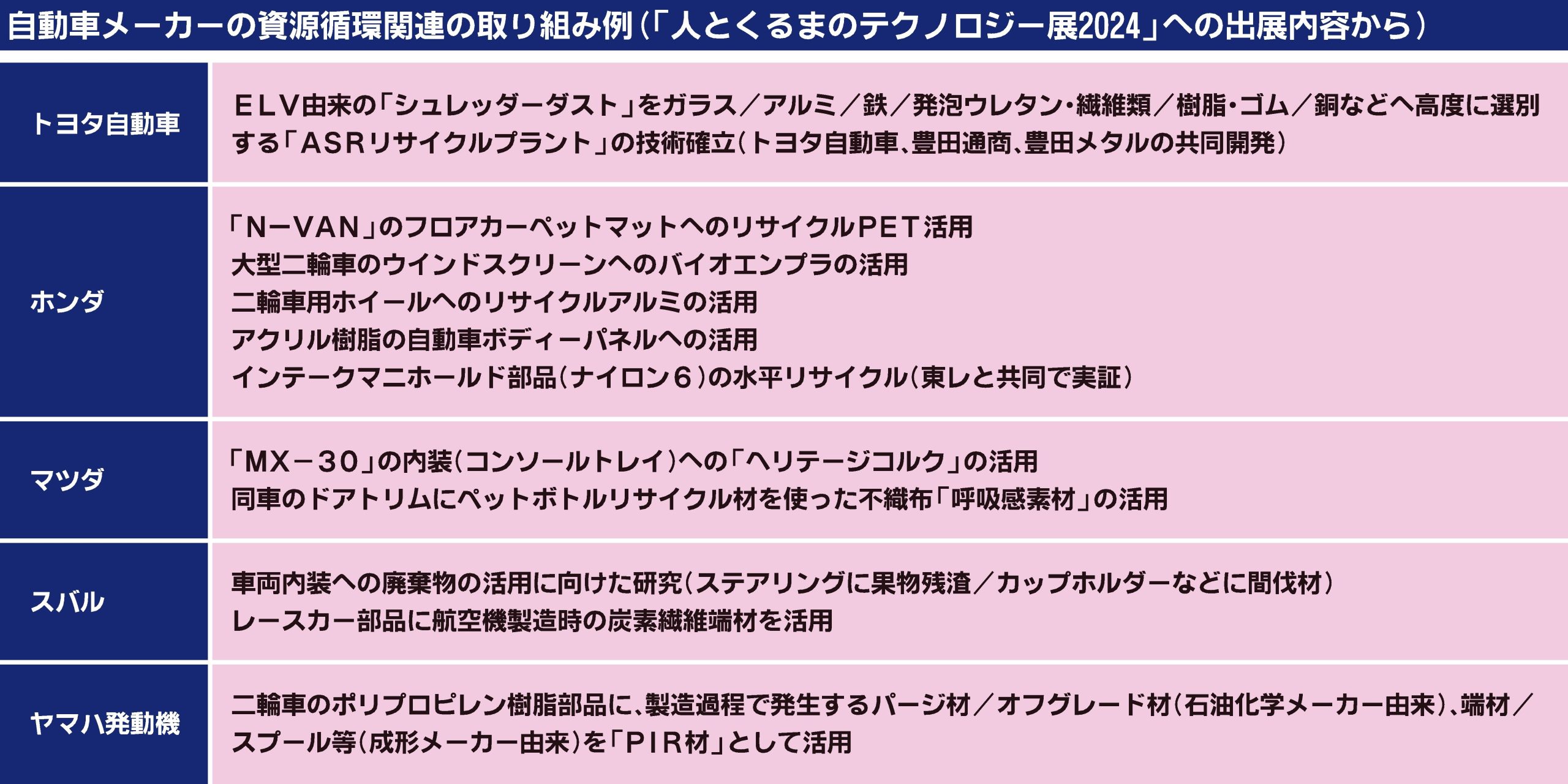関連記事
ELV由来プラ国内回収量 2030年に最大7万㌧ 規制対応・脱炭素化で需要増 矢野経済まとめ
- 2024年7月12日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車部品・素材・サプライヤー

三洋化成、廃プラ溶融混練時に使用する消臭剤 VOC起因の不快さなくす
- 2024年7月19日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

河西工業、ヘッドライニング端材再生のリサイクル材 2027年めどに市場投入 内装部品用に提供
- 2024年7月9日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

欧州電池規則、CFP開示義務化まで1年 競争力確保へ正念場 計画通りに進むかは不透明だが…
- 2024年6月17日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車メーカー

豊田合成、樹脂部品を水平リサイクル 2024年にも量産化 バージン材を半分配合して耐久性を確保
- 2023年9月22日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

ソフト99、旧村上ファンド系エフィッシモの追加TOB賛同を表明 創業家株主の動向が焦点に
- 2026年2月17日 18:10|カー用品・補修部品, 自動車部品・素材・サプライヤー