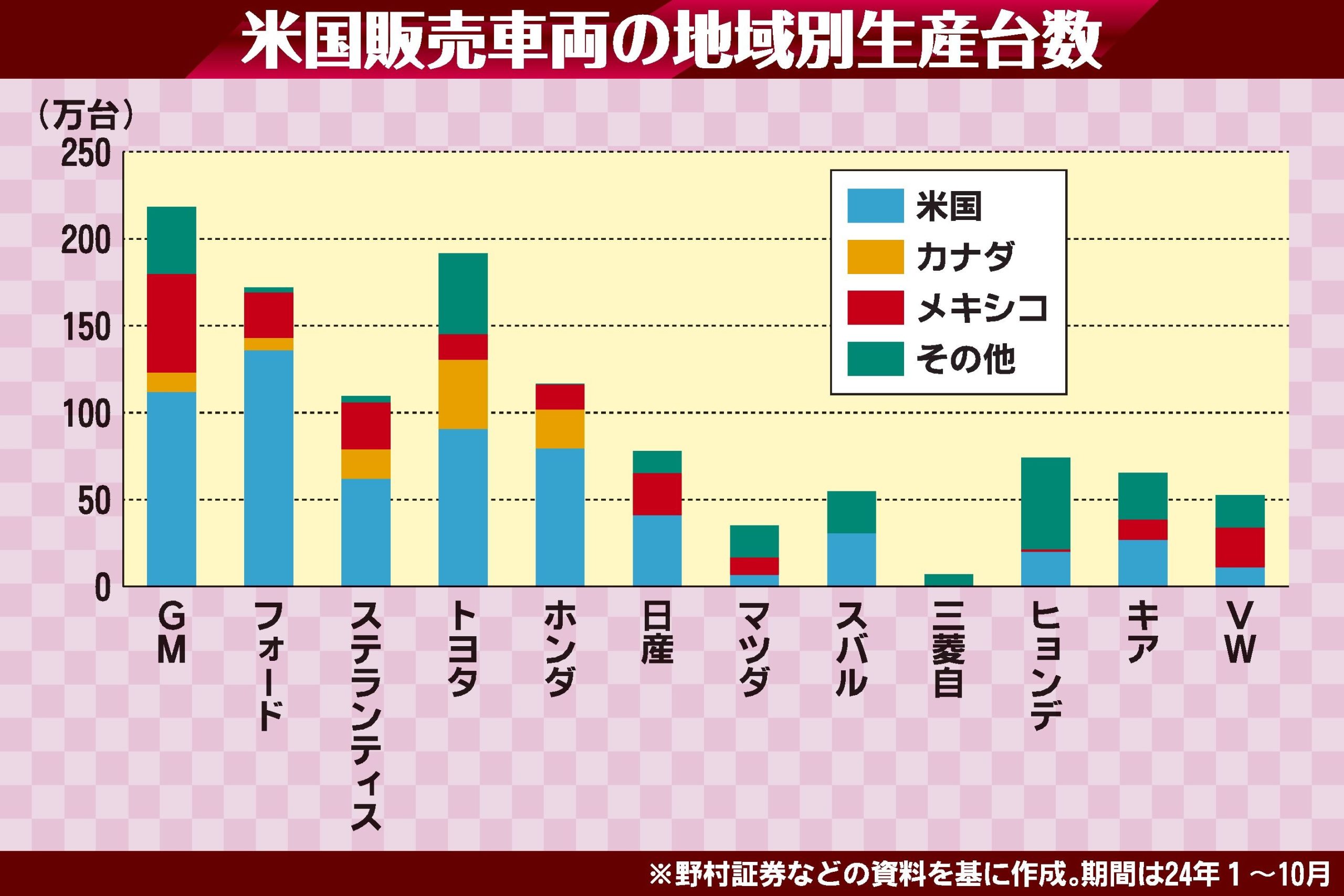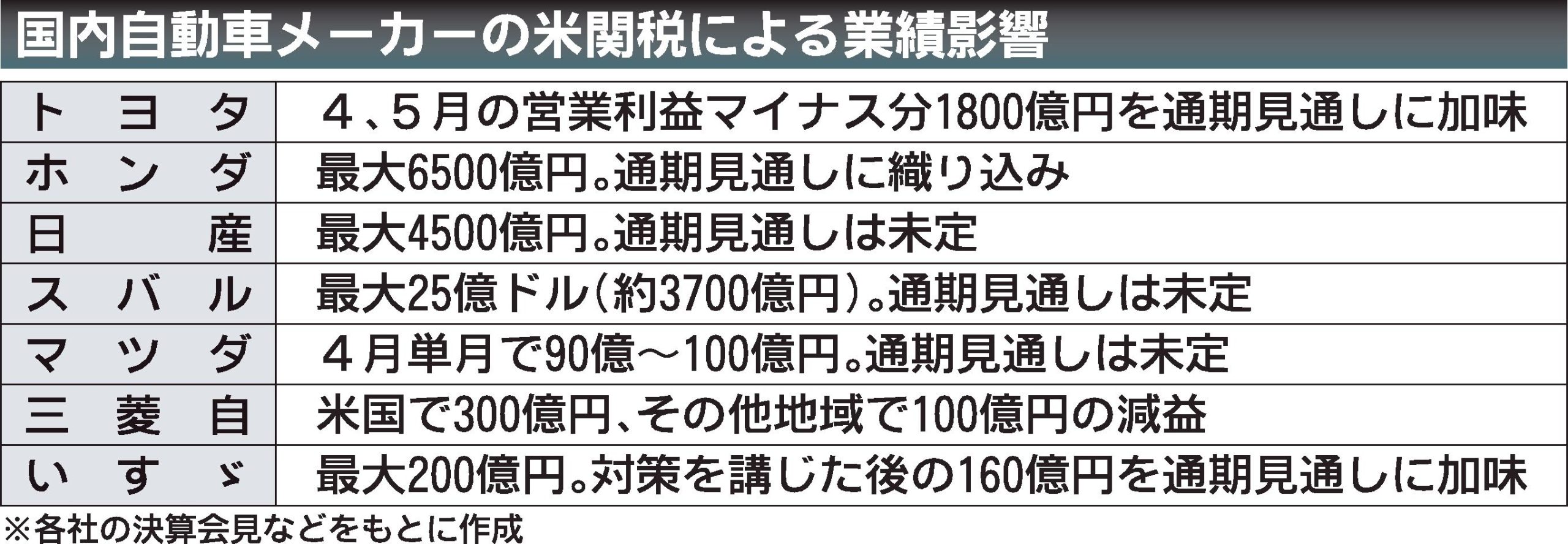関連記事
自工会の片山会長、「早期に関税回避を」 景気刺激策は短期的ならば
- 2025年5月23日 05:00|自動車メーカー

スバル、米国で値上げ検討 トランプ関税の懸念広がる
- 2025年5月21日 05:00|自動車メーカー
ブリヂストン、米国での乗用車用タイヤ生産 2027年までに200万本増
- 2025年5月19日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー
いすゞ、大型トラック生産をUDトラックス上尾工場に移管 改修投資400億円 稼働は2028年予定
- 2026年2月12日 15:50|自動車メーカー