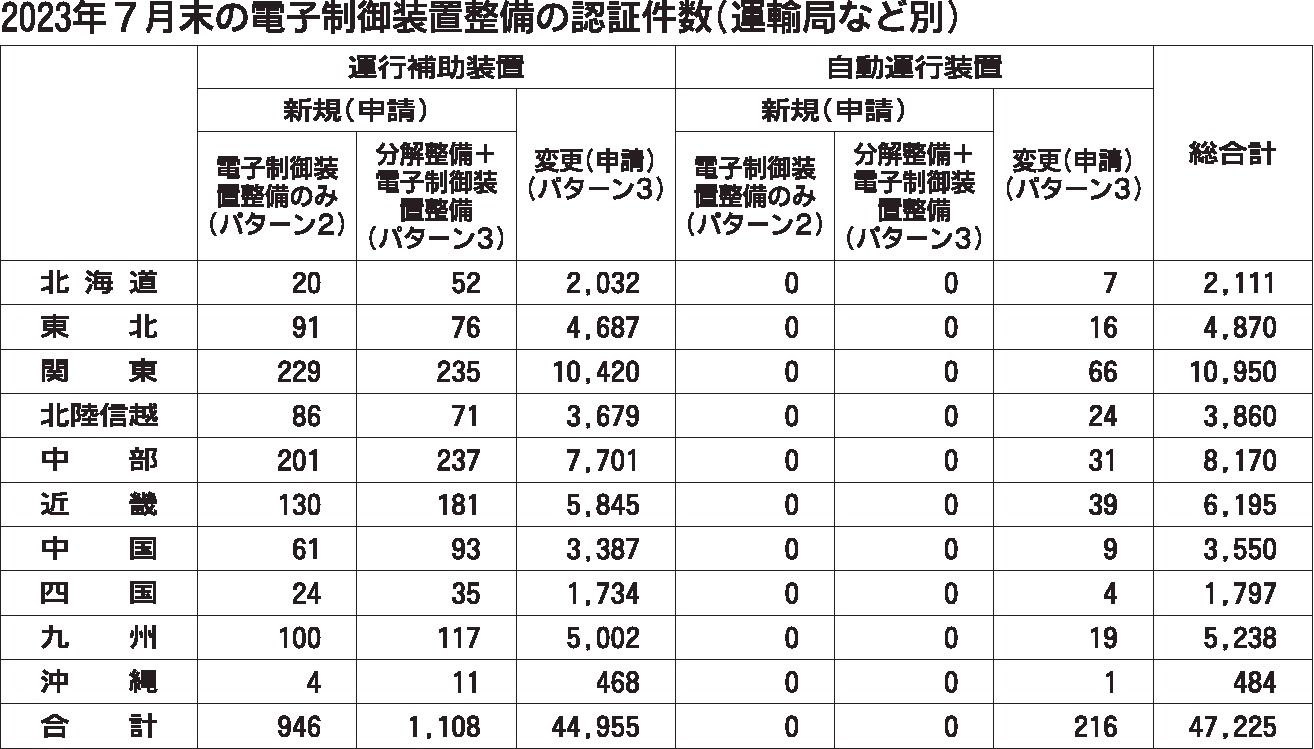関連記事
リサイクル、使用済み車の発生台数が低迷続く 新車回復の影響はまだ 事業者では量から質にシフトする動きも
- 2023年8月16日 05:00|リサイクル

中古車市場、〝タマ不足〟解消で活気戻る 輸出規制やビッグモーターなど不透明要素も足元は3カ月連続プラス
- 2023年8月15日 05:00|中古車流通

メンテナンス関連が好調! カー用品店はピットが予約で満杯 猛暑続き消耗品類に負担 盆休みでさらに活気
- 2023年8月12日 05:00|カー用品・補修部品

〈年頭所感2026〉日本自動車整備振興会連合会 日本自動車整備商工組合連合会 会長 喜谷辰夫
- 2026年1月5日 05:00|自動車整備・板金塗装

政府、自動車整備業の外国人材受け入れを拡大 育成環境を充実して人手不足に対処
- 2025年12月27日 05:00|政治・行政・自治体, 自動車整備・板金塗装

整備事業者、保険を通じ信頼関係深める 特約付加で普段の生活もカバー
- 2025年12月25日 05:00|自動車整備・板金塗装