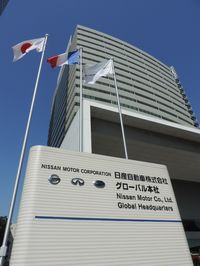日産自動車が事業改革の推進を加速する。グローバルでの自動車生産能力を2018年度の720万台から2022年度までに660万台にまで削減し、2022年度までに人員を4800人削減する計画も工場の直接員を中心に1万2500人削減する。商品ラインナップも見直し、小型車やダットサンなど、不採算モデルの販売を取り止める。収益が悪化している米国事業の立て直しに向けてはフリートを抑えて小売りの比率を大幅に高めて在庫を削減する。自動運転や電動化など、将来の競争力を左右する分野の研究開発投資は増やす一方で、余剰生産能力と人員を削減して収益力を高める。身の丈にあった経営体制に再構築し、2022年度に年間販売600万台で営業利益率6%を確保できる収益力のある自動車メーカーを目指す。
7月25日発表した2019年4-6月期連結決算は営業利益が前年同期比98.5%減の16億円と、ほぼ収支トントンに近いレベルの減益となった。米国での在庫削減やインセンティブの抑制など、販売正常化に向けた取り組みを本格化した影響などから、販売台数が落ち込み、販売活動だけで605億円の減益要因があった。
期中の新車販売は、北米、日本、欧州が不振で、同6.0%減の123万1000台と低迷した。西川廣人CEOは「非常に厳しい結果となったが、在庫は着実に減っており、販売正常化は進んでいる。第1四半期は1番厳しい業績を予想していたが、小売り台数はやや想定を下回ったものの、第2四半期以降、挽回できるレベル」と述べ、通期業績見通しは据え置いた。
足元の業績は厳しいことから事業改革を急ぐ。生産能力を60万台減らして、工場の稼働率を2018年度の69%から86%にまで引き上げる。このため、グローバルで工場のラインの停止や、工場の稼働停止にも踏み切る。2019年度までにインドネシアやスペインなど、8拠点で生産能力を削減する計画に加え、追加で2020年度から2022年度までに6拠点でも生産能力を削減する。これに伴う人員削減規模は2019年度までが6400人、2020年度から2022年度までが6100人で、合計1万2500人と、グローバルでの従業員数の約1割削減して固定費を削減する。
商品ラインナップも見直す。販売が低迷して不採算となっている小型車やダットサン車の生産・販売を取り止める。商品ラインナップをモデル数全体で10%削減する。