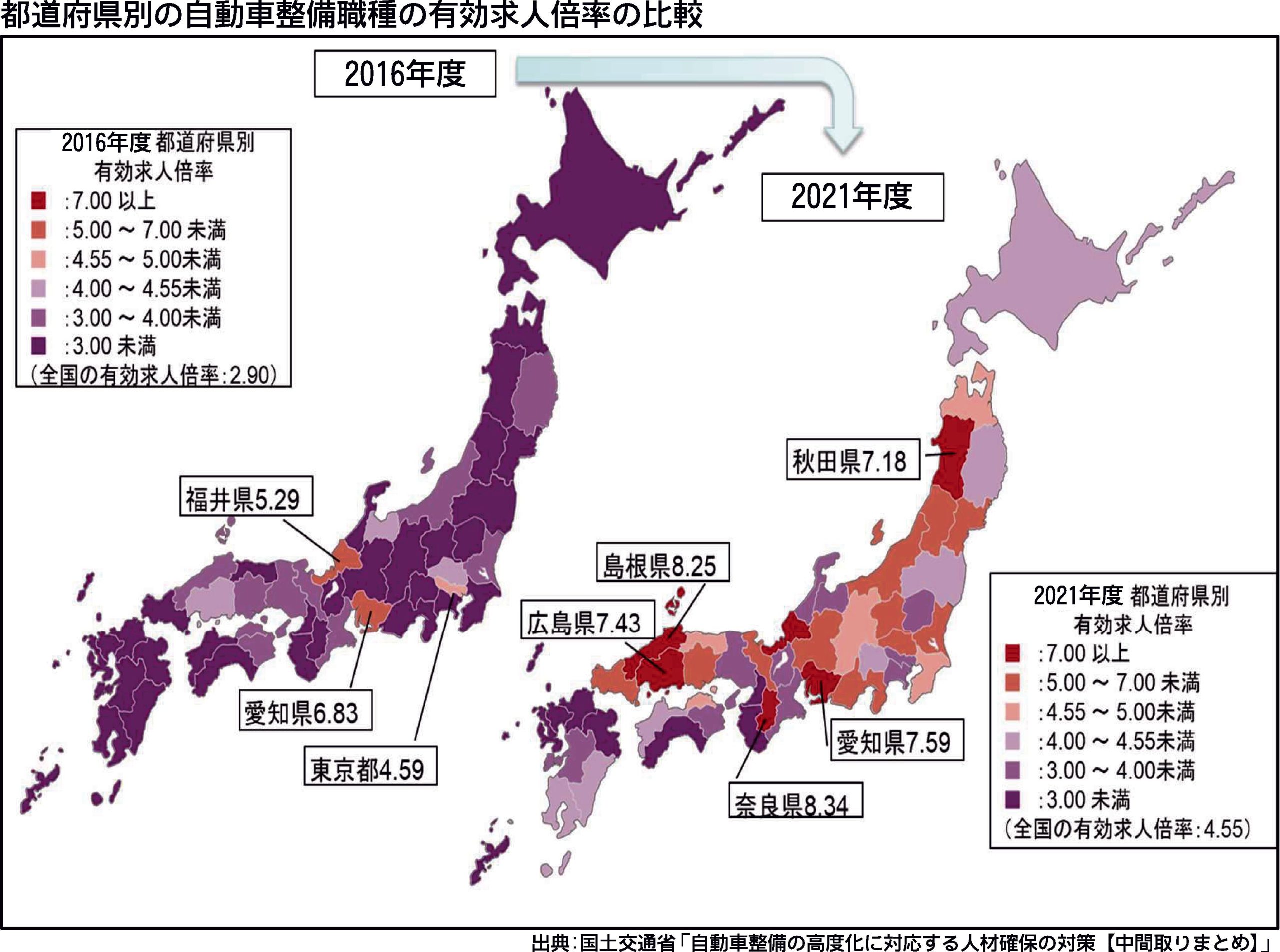関連記事
東京海上と損保ジャパン、指数対応単価引き上げ 7月以降入庫分から 整備業の環境改善へ
- 2025年4月22日 05:00|自動車流通・新車ディーラー, 自動車整備・板金塗装

日整連の動向調査、整備士の過不足感DIが上昇 ディーラーで初改善
- 2025年4月2日 05:00|自動車整備・板金塗装

国交省、整備士の職場づくりガイドラインでアンケート 小規模事業者は実施難しく
- 2025年4月1日 05:00|政治・行政・自治体, 自動車整備・板金塗装
日整連の2024年度実態調査、総整備売上高が18年ぶりに6兆円超える
- 2025年2月6日 05:00|自動車整備・板金塗装

国交省、整備業の職場体験・見学の受け入れマニュアルを作成 事業者や団体の自主的な運営支援
- 2025年1月16日 05:00|政治・行政・自治体, 自動車整備・板金塗装