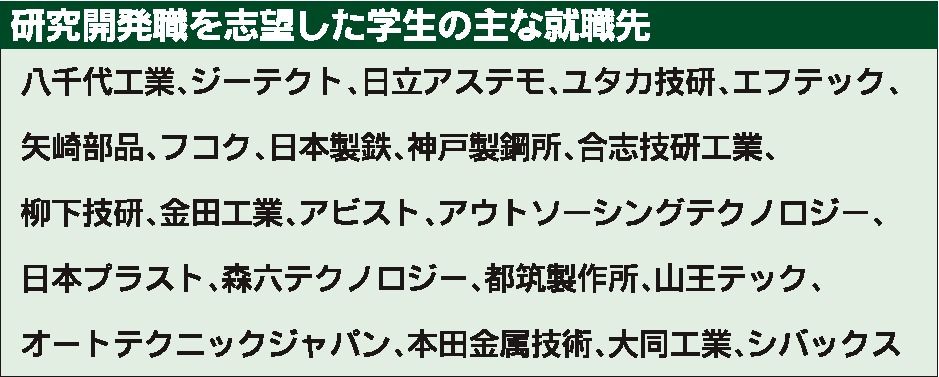関連記事
ホンダ学園、1級整備士課程の定員拡大 関東校は2級と逆転 競合校と差別化図る
- 2024年1月15日 05:00|自動車整備・板金塗装

メーカー系整備学校、学生募集で快適環境を訴求 奨学金増額や設備を改善 理工系学部では「女子枠」導入の動き
- 2023年11月1日 05:00|自動車整備・板金塗装

メーカー系整備学校で学生確保に明暗 系列内で差も 新たな試みで募集強化は不可欠 留学生数は回復の兆し
- 2023年10月4日 05:00|自動車整備・板金塗装

住友ゴム、中国産原材料の調達基準緩和 50%制限にこだわらず 国内化学メーカー生産再編背景に
- 2026年2月13日 11:30|自動車部品・素材・サプライヤー